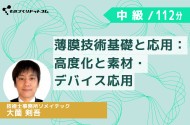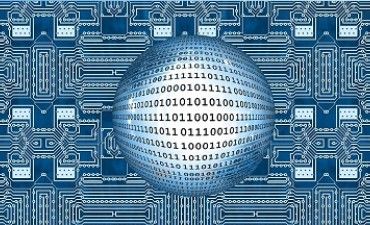■本セミナーの主題および状況
→【量子ドット(Quantum Dots)】は、原子や分子レベルで制御された半導体素材から作られ、その極小さゆえに量子力学的効果が支配的な特性を持つことがあり、これにより特異な光学的、電子的、および電気的特性を示すことがあります。
→量子ドットの【耐久性】につきましては、とくに蛍光特性を考えるときに大切になります。量子ドットは小さいので、半分くらいの原子が表面に配置されています。蛍光特性はその表面の原子の状態によって大きく変わるので、何らかの方法で表面を保護することが不可欠です。アプリケーションに併せて、その保護の方法を設計することが重要になります。
■注目ポイント
★早くから量子ドットの蛍光体としての優れた特性に注目し、論文にあるようなCdSe系では実用化は難しいと考え、毒性回避と耐久性向上を主要な課題として取り組んだ講演者が、ベンチャー設立に繋がったその手法と現状とを解説!
★量子ドットの基礎的物性や合成法をノーベル賞の受賞理由も交えて概説するとともに、実用化を考えた際に必ず直面する耐久性の問題と解決法を解説!
★量子ドットは、表面の割合(体積に対する表面の比率)が大きく、表面の僅かな欠陥で発光特性が変化する。この表面の状態をより深く理解し、耐久性を上げるために蓄積してきたガラスコートの手法を、他の最新の研究とも比較しながら、講演者独自の見解を加えて解説!
セミナー趣旨
量子ドットは、今年のノーベル化学賞に選ばれた分野である。蛍光体としてのこの10年の進展は著しく、発光効率などの特性が飛躍的に向上して価格が劇的に低下し、実用化が本格的に始まった。
本講座では、量子ドットの基礎的物性や合成法をノーベル賞の受賞理由も交えて概説するとともに、実用化を考えた際に必ず直面する耐久性の問題と解決法を解説する。量子ドットは、表面の割合(体積に対する表面の比率)が大きく、表面の僅かな欠陥で発光特性が変化する。この表面の状態をより深く理解し、耐久性を上げるために蓄積してきたガラスコートの手法を、他の最新の研究とも比較しながら、講演者独自の見解を加えて解説する。
【キーワード】
量子ドット、サイズ効果、蛍光体、耐久性、ノーベル化学賞
【講演のポイント】
講演者は、早くから量子ドットの蛍光体としての優れた特性に注目し、論文にあるようなCdSe系では実用化は難しいと考え、毒性回避と耐久性向上を主要な課題として取り組んだ。ベンチャー設立に繋がったその手法と現状とを解説したい。
習得できる知識
量子ドットの基本・概要、特徴
コロイド量子ドットの作製方法、サイズの制御技術、各種の評価法、ガラスコート技術
量子ドットの耐久性向上に関わる技術情報
量子ドットの各分野への応用・最新動向と将来展望
セミナープログラム
- 量子ドットの研究分野の概観
- 量子ドット研究の経緯と今年のノーベル化学賞
- ドープされた量子ドットで期待されたこと
- 量子ドットの基本的な物性と粒成長メカニズム
- 物理的、化学的性質(量子サイズ効果など)
- エネルギー準位の計算方法と留意点
- 量子ドットのサイズと濃度の求め方
- 粒成長メカニズムと発光効率
- 各種量子ドットの合成法・特徴と留意点
- 親水性CdTeの合成法
- 親水散性ZnSeと光化学反応を利用したシェルの付加
- 疎水性CdSeの合成と発展
- 疎水性InPの合成と最近の進展
- ハロゲン化鉛ペロブスカイト、硫化鉛およびカルコパイライト
- 量子ドットのガラスマトリックスへの各種分散法
- バルク体への量子ドット分散:その方法と留意点
- 薄膜への分散およびファイバー形成の方法と留意点
- 微小ガラスカプセル中への分散・安定化
- 量子ドットの各種特性評価の方法
- 単一分子検出法の発明の経緯ともうひとつのノーベル化学賞
- 単一粒子検出とブリンキング
- 発光効率(量子収率)の計算法
- 耐光性の測定・評価法
- 耐久性向上の具体策
- ポリマーを用いる方法
- イオン結晶による閉じ込め
- アルミナ薄膜による被覆
- ガラスカプセル化
- 量子ドットの各応用分野と今後の課題・展望
- ディスプレイ用蛍光体
- 植物工場
- 太陽電池
- 医療用の診断薬
- まとめ
【質疑応答】
セミナー講師
(株)量子材料技術/(国 研) 産業技術総合研究所 (兼業) 取締役 CTO/関西センター 村瀬 至生 氏
セミナー受講料
【1名の場合】44,000円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
受講料
44,000円(税込)/人
前に見たセミナー
関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
全樹脂電池とは?その仕組み、全個体電池との違いをわかりやすく解説
【目次】 近年、エネルギー技術の進化が目覚ましく、特に電池技術はその中心的な役割を果たしています。中でも「全樹脂電池」は、軽量で安全... -
IGBTとは?原理と仕組み、その利用法をわかりやすく解説
【目次】 IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)は、現代の電力エレクトロニクスにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に、... -
熱雑音とは?知っておくべき基礎知識と対策法をわかりやすく解説
【目次】 電子機器や通信システムにおいて、熱雑音は避けて通れない問題です。特に、精密な測定や高性能なデバイスを求める現代においてその... -
SiC MOSFETとは?仕組みや利用における利点と欠点について解説
【目次】 シリコンカーバイド(SiC)金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、次世代のパワーエレクト...