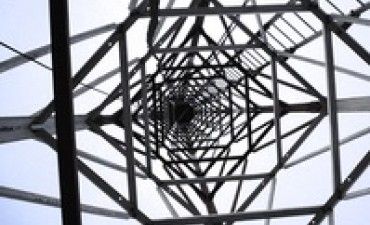半導体パッケージにおける3次元集積実装技術の最新の技術開発動向
★チップレット間の高密度配線を実現するシリコンブリッジ技術の概要とその接合・封止技術について解説!
★チップオンウェハでCu-Cuハイブリッド接合を実現する際の課題と最近の技術開発状況、新規接合材料について解説!
★3次元積層化などのトレンドに対して、必要となる材料とその開発トレンドについて紹介!
セミナープログラム
【第1講】 半導体集積化における3次元集積実装技術の最新動向
【時間】 10:30-12:00
【講師】国立研究開発法人産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 3D集積システムグループ 研究グループ長 菊地 克弥 氏
【講演主旨】
これまでの国家プロジェクトや国際会議を中心に3次元集積実装技術の研究開発動向をお話しいたします。
【習得できる知識】
・3次元集積実装技術の基礎知識
・国家プロジェクトにおける3次元集積実装技術の研究開発の流れ
・3次元集積実装技術の最新の技術動向
【プログラム】
1.はじめに
2.国家プロジェクトを通じた3次元集積実装技術の研究開発
2-1 国家プロジェクトでの3次元集積実装技術の要素技術開発(FY1999~FY2012)
2-2 3次元集積実装技術による車載用障害物センシングデバイス開発(FY2013~FY2017)
2-3 ハードウェアセキュリティ研究における3次元集積実装技術の研究開発(FY2015~FY2021)
2-4 3次元集積実装技術によるIoTデバイス試作開発拠点の構築(FY2016~FY2017)
2-5 ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業における3次元集積実装技術の研究開発(FY2021~)
3.国家プロジェクト外での産総研での3次元集積実装技術の研究開発の取り組み
4.3次元集積実装技術の最新の技術研究動向 ~IEDM 2021、ECTC2022、VLSI Symposium 2022~
4-1 IEDM2021におけるMore than Moore技術研究動向
4-2 ECTC2022におけるMore than Moore技術研究動向
4-3 VLSI Symposium 2022におけるMore than Moore技術研究動向
5.まとめ【質疑応答】
【第2講】 チップレットを進化させるシリコンブリッジパッケージとその接合・封止技術
【時間】 13:00-14:15
【講師】IBM 堀部 晃啓 氏
【講演主旨】
コンピューターシステムの絶え間ない性能向上が求められるなか、半導体デバイスの集積化および性能向上において、半導体素子の集積限界とチップサイズ拡大の限界を乗り越えるためにチップレットパッケージが大きな注目を集めているが、チップ間のデータ転送速度がその性能向上の鍵となる。本講座ではそのチップレット間の高密度配線を実現するシリコンブリッジ技術の概要とその接合・封止技術について解説する。
【キーワード】
チップレットパッケージ、シリコンブリッジ、高密度配線、微細バンプ接合、アンダーフィル
【プログラム】
1.IBM Researchの概要
2.AI Hardware Center programの概要
3.Direct Bonded Heterogeneous integration(DBHi)
3.1 DBHiの概要
3.2 DBHiの接合技術
3.3 DBHiの封止技術
3.4 surface-DBHi
4.まとめ
【質疑応答】
【第3講】 チップオンウェハCu-Cuハイブリッド接合用 新規接合材料の開発
【時間】 14:30-15:45
【講師】三井化学株式会社 ICTソリューション研究センター 茅場 靖剛 氏
【講演主旨】
人工知能やデジタルトランスフォーメーションなどの急激な普及に伴い、大量のデータを高速で処理する必要があり、半導体集積回路(IC)の性能向上の要求がこれまで以上に高まっている。ICの高性能化手法として、従来のトランジスタ微細化による手法と並び、ICチップの3次元積層手法が重要な技術となりつつある。3次元ICチップ積層では、はんだ接合が用いられてきたが、チップ間の広帯域データ通信のため、20μm以下の狭ピッチ電極でチップ同士を電気的に接続出来るCu-Cuハイブリッド接合技術の実現が望まれている。本講座では、チップオンウェハでCu-Cuハイブリッド接合を実現する際の課題と最近の技術開発状況、および弊社の開発した新規接合材料について講演を行う。
【キーワード】
Cu-Cuハイブリッド接合、チップレット、チップオンウェハ、3D積層、2.5D/3D、ヘテロ集積
【講演ポイント】
講演者は、半導体デバイス用材料のみでなく、実装プロセスの研究開発にも従事している。
本講演では、チップオンウェハCu-Cuハイブリッド接合における課題と、提案されている各種解決方法について
講演者の知見を基に解説を行う。
【習得できる知識】
・チップオンウェハCu-Cuハイブリッド接合の基礎から最近の技術開発動向までを学ぶことが出来ます
・無機接合材料と有機接合材料の特徴と課題について学ぶことが出来ます
・弊社開発の新規接合材料の特性について学ぶことが出来ます
【プログラム】
1.チップオンウェハCu-Cuハイブリッド接合概論
1.1 チップオンウェハCu-Cuハイブリッド接合が必要とされる技術背景
1.2 チップオンウェハCu-Cuハイブリッド接合プロセスと課題
1.3 各種ダイシング方法(ブレード、ステルス、プラズマ)
1.4 チップ接合方法(ダイレクトプレイスメント、コレクティブ、ギャップフィル)
1.5 最近のデバイス開発例(ロジック、メモリー)
1.6 まとめ
2.弊社開発新規接合材料のご紹介
2.1 無機接合材料と有機接合材料の特徴と課題
2.2 弊社開発接合材料のコンセプト
2.3 コンセプトの検証
2.4 材料の信頼性
2.5 まとめ
【質疑応答】
【第4講】 3次元半導体パッケージに向けた耐熱樹脂材料への要求特性と開発動向
【時間】 16:00-17:15
【講師】東レ株式会社 富川 真佐夫 氏
【講演主旨】
半導体の高機能化にともない、半導体チップサイズの巨大化に伴うチップレット化とそれを効率よくパッケージ化するための3次元積層化などのトレンドに対して、必要となる材料とその開発トレンドについて紹介する。
【講演ポイント】
現在、開発が進められている半導体の3次元パッケージに必要な材料について、現状をまとめた。電子材料の開発状況、動向の理解が進む。
【習得できる知識】
・半導体パッケージの進化に向けた材料
・各材料設計の考え方
【プログラム】
1.半導体の技術開発トレンド
1.1 チップレット化
1.2 3次元積層化
2.3次元半導体パッケージ関連材料
2.1 半導体実装材料
2.2 熱伝導性材料
2.3 高精細感光性耐熱材料
2.4 低誘電・低Tanδ材料
【質疑応答】
セミナー講師
- 第1部 国立研究開発法人産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 3D集積システムグループ 研究グループ長 菊地 克弥 氏
- 第2部 IBM 堀部 晃啓 氏
- 第3部 三井化学株式会社 ICTソリューション研究センター 茅場 靖剛 氏
- 第4部 東レ株式会社 富川 真佐夫 氏
セミナー受講料
【1名の場合】55,000円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
受講料
55,000円(税込)/人