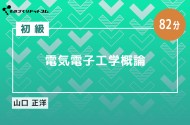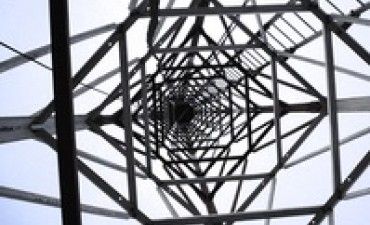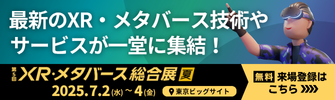類似セミナーへのお申込みはこちら
フィラー表面処理、低フィラー化、配向制御など
熱伝導率向上へのヒントを詳解!
これからのクルマには、どんな放熱材料が求められるのか、実際の使われ方から考察!
セミナープログラム
<10:00〜11:30>
1.車載電子製品の放熱・耐熱技術とTIMへの要求性能
(株)デンソー 神谷 有弘 氏
【講座概要】
自動運転技術の開発に伴い、新たな電子制御システムの増加が顕著になっています。各電子製品は小型軽量化を求められ、熱設計は厳しくなる一方です。そこで、放熱対策として使われるTIMは、さまざまな種類が開発されていますが、各特性を理解して最適なものを使いこなすことが必要です。事例に基づきTIMに必要な特性を理解いただけるよう解説いたします。
1.カーエレクトロニクスの概要
1.1 クルマに求められる価値
1.2 CASE時代の電子製品の特長
2.車載電子製品と実装技術への要求
2.1 小型軽量化
2.2 高信頼性
2.3 小型化と熱設計の関係
3.小型実装技術
4.熱抵抗の考え方とTIMの特性
4.1 熱抵抗とは
4.2 接触熱抵抗のモデル
4.3 低接触熱抵抗のためには
5.電子製品の放熱技術とTIMの使い方
5.1 基板からの放熱性向上
5.2 材料特性と理解する
6.パワーデバイス放熱構造とTIMへの要求
6.1 パワーデバイス放熱構造の動向
6.2 片面放熱構造とTIMへの期待
6.3 両面放熱構造におけるTIMの使い方
7.将来動向
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
<12:10〜13:40>
2.形状異方性フィラーの配向制御技術と放熱シートの高熱伝導化
バンドー化学(株) 向 史博 氏
【講座概要】
放熱シートは電子機器の放熱設計における問題解決の一手段であり、電子機器の今後更なる発展に併せて際限のない性能向上が望まれる部材である。本講では放熱シートの高熱伝導率化の一処方として形状異方性フィラーの配向制御を挙げ、その適用効果について紹介する。
1.サーマルインターフェースマテリアルの概要
1.1 サーマルインターフェースマテリアルの製品分類
1.2 放熱シートの要求機能と課題
2.形状異方性フィラーの配向制御による放熱シートの高熱伝導化
2.1 フィラー充填複合物の高熱伝導化技術
2.2 形状異方性フィラーの特徴と狙いとするフィラー充填構造
2.3 カーボンファイバー垂直配向シート(HEATEX 導電タイプ)
2.4 六方晶窒化ホウ素垂直配向シート(HEATEX 絶縁タイプ)
3.配向制御高熱伝導シートの特性
3.1 特性評価
3.2 配向状態・配合因子による影響
4.まとめ
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
<13:50〜15:20>
3.窒化物フィラーの表面処理、高充填技術とコンポジット材料の熱伝導率向上
富山県立大学 真田 和昭 氏
1.窒化物フィラーの種類と熱伝導率
2.窒化物フィラーコンポジットの粘度予測
2.1 コンポジットの粘度予測式と適用範囲
2.2 フィラー粒度分布を考慮したコンポジットの粘度予測理論
3.窒化物フィラーの最密充填技術と低フィラー化技術
3.1 フィラー最密充填理論
3.2 フィラー最密充填によるコンポジットの高熱伝導率と低粘度の両立
3.3 コンピューターシミュレーションを活用した新しい充填構造設計手法
3.4 フィラーのハイブリッド化とネットワーク構造形成による低フィラー化技術
4.窒化物フィラーの表面処理技術
4.1 窒化物フィラーの表面処理事例
5.窒化物フィラーコンポジットの熱伝導特性評価
5.1 コンポジットの熱伝導率予測式
5.2 国内外での窒化物フィラーコンポジットの開発動向
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
<15:30〜17:00>
4.高熱伝導放熱シートの熱伝導率測定、評価
茨城大学 太田 弘道 氏
【講座概要】
日本工業規格を紹介する経済産業省のWebページにおいて平成30年11月に新たに制定された重要な規格として「スマートフォン等に用いられるグラファイトシートの放熱性に関するJIS」がその筆頭としてあげられた。制定にかかわった立場から、この規格を中心として、その他に広く用いられている測定法の原理や使い勝手などについても現場の経験に基づいて解説する。
1.伝熱の測定の原理
1.1 定常測定と非定常測定
2.フラッシュ法
2.1 キセノンフラッシュ法
2.2 レーザフラッシュ法
3.複合相の測定
3.1 現場での意味
3.2 定常法
3.3 フラッシュ法
4.周期加熱法
4.1 JIS
4.2 未規格化部分の進展
4.3 熱物性顕微鏡
【質疑応答・個別質問・名刺交換】
セミナー講師
1. (株)デンソー 基盤ハードウェア開発部 神谷 有弘 氏
2. バンドー化学(株) 新事業推進センター 技術部 向 史博 氏
3. 富山県立大学 工学部 機械システム工学科 教授 博士(工学) 真田 和昭 氏
4. 茨城大学 大学院理工学研究科 量子線科学専攻 教授 工学博士 太田 弘道 氏
セミナー受講料
1名につき60,000円(消費税抜き・昼食・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税抜)〕
受講料
66,000円(税込)/人
類似セミナー
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
HVDC(高圧直流送電)とは?HVDCが描く未来、再エネ社会を繋ぐ革新送電
【目次】 現代社会において、電力は私たちの生活を支える不可欠なインフラです。しかし、その電力供給のあり方は、気候変動問題への対応やエ... -
エネルギーハーベスティングとは?自然の力がエネルギーの新しい形に、その現状と展望を解説
【目次】 エネルギーハーベスティングは、私たちの身の回りに存在する太陽光、熱、振動、電波といった微小なエネルギーを「収穫... -
全樹脂電池とは?その仕組み、全個体電池との違いをわかりやすく解説
【目次】 近年、エネルギー技術の進化が目覚ましく、特に電池技術はその中心的な役割を果たしています。中でも「全樹脂電池」は、軽量で安全... -
ギガキャストとは?ギガキャスト金型がもたらす自動車製造の進化、技術の全貌とその影響
【目次】 自動車産業は、常に革新と進化を求められる分野です。その中で、近年注目を集めているのが「ギガキャスト」という技術です。ギガキ...