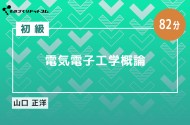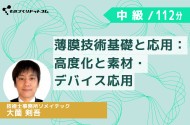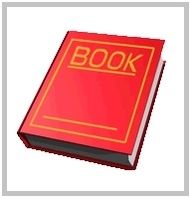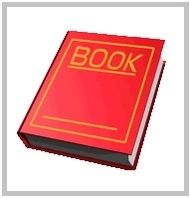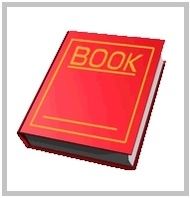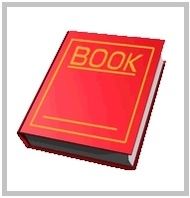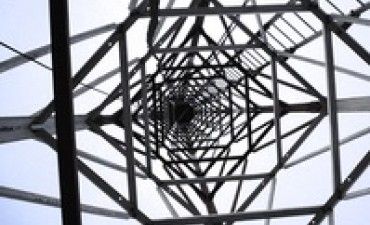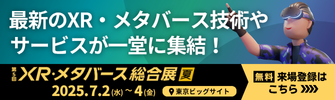積層セラミックスコンデンサ(MLCC)における材料開発と多層化・大容量化・高信頼性化と部材技術
★MLCCの高積層化技術と、それに伴って生じるトラブル、解決方法を歴史から始まって最新情報まで解説!
★MLCCの長所、短所など基本的な内容を分かりやすく説明!
★具体事例を示して、小型化の実現方法の考え方や、不具合の具体的内容とそれに対する対策を検討し、信頼性向上の方策を考えていく!
セミナープログラム
第1部 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の高積層化・大容量化・高信頼性の技術動向と今後の展望
【12:30-14:00】
防衛大学校 名誉教授、大阪公立大学 客員教授 工学博士 山本 孝 氏
【講演主旨】
積層セラミックスコンデンサー (MLCC) はスマートホンやパソコンに代表されるように小型化、高性能化、省電力化が進んだ電子機器で数多く使用されている代表的な受動部品である。特に、内部電極をNi金属に代えたNi内電MLCCはNi金属の低コスト化を特徴にして大容量・小型化が急激に進んだ。チップサイズは年々小型化し0201タイプ (0.2×0.1mm) の実用化も始まっている。アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに取って代わる大容量MLCCにおいても、材料の誘電率の向上、誘電体層の薄層化、多層化が進んでいる。近年、自動車のEV化が進み、高温対応MLCCS、特に高信頼性対応の需要も急増している。近い将来、5G/beyond5G および6Gにおいても誘電体材料は必要とされる。
当講座ではNi内電MLCCの材料から始まって、高積層技術、更に将来展望まで幅広く、且つ詳細に解説を行う。
【キーワード】
MLCC,高積層MLCCコンデンサ―,高容量Ni-MLCC,EV対応MLCC
【講演ポイント】
MLCCの高積層化技術と、それに伴って生じるトラブル、解決方法を歴史から始まって最新情報まで解説する。
【習得できる知識】
積層コンデンサ (MLCC) 材料の基礎から応用まで
MLCC原料から完成体まで
MLCCの高積層・高容量の技術
積層の技術、その問題点
【プログラム】
- MLCCのサイズの変遷、MLCC世界ランキングと市場、世界最小MLCCの出現
- MLCC事情、スマートホン・自動車に搭載される電子部品、MLCCの形状と規格
- MLCCをLCR等価回路で考えると、車のEV化に向けて低ESLコンデンサの利用
- MLCCの小型・大容量化の展開の歴史から現状
- 材料から見たBaTiO3+希土類+アクセプタ+固溶制御材+焼結助剤の歴史
- COG,NP0特性のCu内電MLCC
- MLCCの小型化、容量密度の進化、誘電体層薄層化の進化
- Ni-MLCCの製造プロセス、グリーンシートの技術動向
- 高信頼性MLCCに必要なこと、微小粒径、コア・シェル構造の利点
- 薄膜用MLCCに求められる特性、水熱BaTiO3
- 固相法によるBaTiO3の微細化, 微少・均一BaTiO3のためのアナターゼTiO2
- 固相反応によるBaTiO3 の反応メカニズム, 水蒸気固相反応法、BaTiO3の低温反応、水で加速する室温固相反応 (BaTiO3)
- 粉砕と分散とは、メデイアのサイズ、メデイアの材質
- 車載用MLCC、X8R規格のMLCC (Ba,Ca,Sn)TiO3の特性評価、Ca,Snの役割, 応力印加効果
- 電圧印加で容量が増加するMLCCとは, PZT薄膜のキュリー点が600℃???
- 高積層・高容量MLCCのためのNi内部電極用Ni微粒子、供材
- 2段焼成法のNi内部電極の効果,カバーレッジの向上
- Ni内部電極の成形メカニズム (膜断面の観察), Ni内部電極の連続性 (カバーレッジ) 向上のメカニズム
- Ni電極向上のために (Ni微粒子径、粒度分布、供材添加), Ni微粒子への添加効果 (Ni-Cr, Ni-Sn)
- Ni電極印刷法 (グラビア印刷)
- MLCC外部電極 (高温対応)
- MLCCの信頼性I KFM法, MLCCの信頼性II E-J評価
- 絶縁劣化メカニズム
- 最近のMLCC研究動向
- まとめ
- 付記) 現象論的熱力学を用いたBaTiO3の特性シミユレーション
【質疑応答】
第2部 MLCCの構造、誘電体及び特性と設計課題
【14:15-15:30】
(株)トーキン セールス&マーケティング本部 アプリケーションエンジニアリング エキスパート 高木 滋民 氏
【講演主旨】
MLCCは積層セラミックキャパシタという電気を蓄えたり放出したりする電子部品で要は電圧を安定させたり、ノイズを取り除いたりする電子部品です。通信機器や車載分野などあらゆる電子機器には必ず使うと言って良いほど使われており欠かせない部品です。この様に重要部品のひとつであるMLCCですが、MLCCの基本から分かりやすく解説し、長所、短所、構造、そして誘電体の特性を理解し設計において注意事項について理解していただくことを目的としています。
【キーワード】
コンデンサ、MLCC、X7R、C0G、誘電体、誘電率、MLCCの構造、温度特性、DCバイアス特性、エージング特性、クラック、KEMET
【講演ポイント】
MLCCの長所、短所など基本的な内容を分かりやすくご説明致します。
【習得できる知識】
MLCCの選定において注意すべき点を理解し、部品選定に役立つ知識を身に着けることができる。
【プログラム】
- MLCCの特徴と他のコンデンサとの違い
- 誘電体の特徴
- MLCC特性と設計上考慮する内容
- 静電容量 vs 温度特性
- 静電容量 vs バイアス特性
- ESRとリップル電流
- クラック
- KEMET製 MLCCのラインアップ
- 会社紹介
- フォーカスエリア
- ラインアップのご紹介
【質疑応答】
第3部 MLCCを中心とした車載電子機器における実装技術・信頼性確保とその評価法
【15:45-17:00】
(株)デンソー 電子PFハードウェア開発部 神谷 有弘 氏
【講演主旨】
車両の電動化と自動運転技術開発の進展に伴い、車両の電子制御化とパワーエレクトロニクスの応用展開が進んでいます。車両に搭載される電子機器が増加し、小型軽量化が求められています。小型については、MLCCへの代替、見直しを行うことで小型化を実現できます。各種事例を通して小型軽量化と、信頼性向上について説明いたします。
【キーワード】
車載電子製品、MLCC、小型化、信頼性、評価方法
【講演ポイント】
具体事例を示して、小型化の実現方法の考え方を学ぶことや、不具合の具体的内容とそれに対する対策を検討しながら、信頼性向上の方策を考えることができます。
【習得できる知識】
小型実装技術の考え方と、信頼性を考慮しての製造技術のバランスを考える視点とを身に着けることができる。
【プログラム】
- 車載電子製品は何のために存在するのか
- クルマ社会を取り巻く課題
- 環境とエネルギー問題への対応
- 安全(自動運転技術)
- 電子プラットフォーム設計
- CASE時代の車載電子製品への要求
- 小型軽量化が求められる背景
- 車載電子製品の小型化動向
- 信頼性の重要性
- 車載電子製品の小型実装技術
- 実装技術とは
- 実装技術と熱設計の関係
- センサの小型化
- ECU製品の小型化設計
- 部品小型化の検討(MLCCを中心に)
- セラミックコンデンサのサイズ動向
- セラミックコンデンサの特徴
- セラミックコンデンサを使った小型化検討(事例)
- 部品内蔵技術
- 部品内蔵基板とMLCC
- 部品内蔵技術の普及
- 信頼性の基礎
- ストレス強度モデル
- S-N曲線
- 加速試験
- 複合試験の重要性
- 電子部品の故障事例と対策
- 電子製品の環境と不具合事例
- イオンマイグレーション
- ウィスカ
- セラミックコンデンサにまつわる不具合事例
- 微小部品搭載における注意点
- 将来動向
- 機電一体製品と樹脂封止
- 樹脂封止技術への期待と注意点
- 車両電動化とワイドバンドギャップデバイスへの期待
- ワイドバンドギャップデバイス実装の課題
- 電動化とインバータの搭載形態
【質疑応答】
セミナー講師
第1部 防衛大学校 名誉教授、大阪公立大学 客員教授 工学博士 山本 孝 氏
第2部 (株)トーキン セールス&マーケティング本部 アプリケーションエンジニアリング エキスパート 高木 滋民 氏
第3部 (株)デンソー 電子PFハードウェア開発部 神谷 有弘 氏
セミナー受講料
【1名の場合】44,000円(税込、テキスト費用を含む)
2名以上は一人につき、11,000円が加算されます。
受講料
44,000円(税込)/人