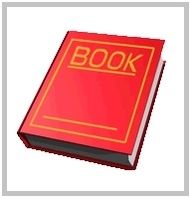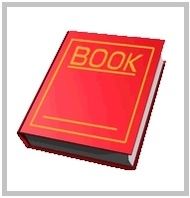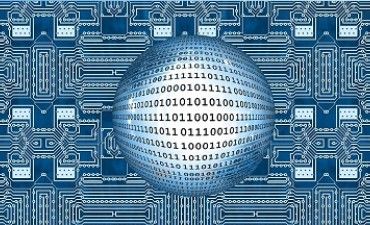以下の類似セミナーへのお申込みをご検討ください。
★鉛フリー、高耐熱、低温焼結、無加圧接合、、、
生産性、接続信頼性向上につながる接合材料・技術を探る
講師
1.(株)東芝 生産技術センター 実装技術研究部
博士(工学)平塚 大祐 氏
2.(株)日立製作所 研究開発グループ 生産イノベーションセンタ
プロセス研究部 第2研究ユニット 宮崎 高彰 氏
3.(地独)京都市産業技術研究所 金属系チーム
次席研究員 博士(工学) 塩見 昌平 氏
4.日立化成(株) 先端技術研究開発センタ
専任研究員 工学博士 中子 偉夫 氏
5.大同大学 工学部 電気電子工学科
教授 博士(工学) 山田 靖 氏
受講料
1名につき60,000円(消費税抜き・昼食・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税抜)〕
プログラム
< 10:00〜11:10>
1.パワー半導体の高温動作を可能にするAgナノ粒子接合材料の開発と焼結接合技術
(株)東芝 平塚 大祐 氏
【講演概要】
パワーデバイスの高温動作を可能にする高温対応ダイマウント技術の中で、特に耐熱性、放熱性に優れたAgナノ粒子の焼結接合技術について基礎から説明します。特に高温動作化で課題となる高温脆化現象については、メカニズムの解明とそれに基づいた信頼性向上技術について解説します。
1.はじめに
1.1 高温対応の必要性(パワーデバイスの高温動作化、リフロー実装)
1.2 現行ダイボンド材料例と、高温対応材料に求められる特性
2.高温対応ダイボンド材料
2.1 高温対応ダイボンド材料の分類
2.2 鉛フリー高融点はんだ接合
2.3 液相拡散接合(CuSn, NiSnなど)
2.4 銀(Ag)ナノ粒子接合
2.5 まとめ(特性,制約等のベンチマーク)
3.Agナノ粒子とその焼結接合
3.1 Agナノ粒子の微細化によるメリット/デメリット
3.2 焼結技術の分類と焼結条件との関係
3.3 加圧接合と無加圧接合の特長と課題
4.Agナノ粒子の焼結接合の高信頼化
4.1 耐熱性と高温脆化現象
4.2 高温脆化メカニズムの解明
4.3 耐熱性を向上するMS2NP法
【質疑応答・名刺交換】
<11:20〜12:30>
2.高温下でも劣化しない鉛フリーはんだ接合技術
(株)日立製作所 宮崎 高彰 氏
【講演ポイント】
近年、省エネルギー化の観点から電力を高効率に制御するためのキーコンポーネントであるパワーモジュールの開発が進んでいる。パワーモジュールでは小型化のため高パワー密度化が進んでおり、半導体素子の発熱は上昇する傾向にあるため、はんだ接合部にもこれまで以上に高温信頼性が要求されている。
そこで、パワーサイクル試験による接合部の劣化メカニズムの解明と高温環境下で信頼性を維持可能なSn系はんだおよびSnを用いた液相拡散接合技術について解説します。
1.背景
1.1 パワーエレクトロニクス市場動向
1.2 ダイボンド材への要求と候補材料
2.Sn系はんだの耐熱性向上
2.1 接合界面の安定性向上
2.2 添加元素によるSn母相のパワーサイクル信頼性向上
3.金属間化合物を利用した接合
3.1 Cu粉/Sn粉複合はんだ
3.2 液相拡散接合
4.まとめ
<13:10〜14:20>
3.低温焼結接合に向けたCuナノ粒子の作製と応用
(地独)京都市産業技術研究所 塩見 昌平 氏
【講演ポイント】
高温動作可能なパワーデバイスの実用化の中で、熱マネジメントを含めた周辺技術の確立はきわめて重要な課題であり、中でも、従来のはんだに代わる接合技術が求められています。本講座はこのような接合技術の進展と研究開発について理解を深めることができます。 高温動作可能なパワーデバイスの実用化の中で、熱マネジメントを含めた周辺技術の確立がきわめて重要です。 金属ナノ粒子による低温焼結接合は、電気、熱伝導特性に優れ、かつ高温信頼性を有した接合技術として注目されています。 本講演では、このような焼結接合材料に向けた、ウエットプロセスによるCuナノ粒子の作製に関する取り組みについて紹介します。
1.背景
2.金属ナノ粒子の合成と評価
2.1 ウエットプロセスによる金属ナノ粒子の合成
2.2 合成条件の最適化,設計指針
2.3 ナノ粒子の評価
3.Cuナノ粒子の合成
3.1 Cuナノ粒子合成条件の最適化
3.2 Cuナノ粒子の形態制御
4.Cuナノ粒子による焼結接合
4.1 接合強度に影響を及ぼすファクター
4.2 接合材料に向けたCuナノ粒子の材料設計
5.まとめ
【質疑応答・名刺交換】
<14:30〜15:40>
4.無加圧接合可能な焼結Cu接合材料の開発
日立化成(株) 中子 偉夫 氏
【講演ポイント】
パワーモジュールの高容量密度化に伴い、パッケージ用部材、特にダイボンド材に高熱伝導、高接続信頼性が要求されています。従来の高鉛はんだでは、低い熱伝導率(30W/m・K),環境負荷物質(Pb)の含有、接続信頼性の不足が問題となっており、それに対し焼結金属接合材が注目されております。我々は、焼結銅接合材の開発に取り組んでおります。これは、高熱伝導性、高接続信頼性、無加圧での接合、廉価な材料コスト、環境負荷物質の不含といった特徴ある材料です。本講演ではその内容について紹介します。
1.開発背景
1.1 新規な高熱伝導,高接続信頼性のダイボンド材要求の背景
1.2 焼結Ag接合材の特長と信頼性
2.無加圧接合可能な焼結Cu接合材
2.1 無加圧接合と条件の影響
2.2 接合層の特性
2.3 接続信頼性の比較
3.焼結Cu接合材の応用
3.1 厚膜の焼結Cu層の形成
3.2 Cuクリップの接合
【質疑応答・名刺交換】
<15:50〜17:00>
5.銅ナノ粒子を用いた高耐熱接合技術
大同大学 山田 靖 氏
【講演ポイント】
SiCやGaNを用いたパワー半導体デバイスは、200℃以上の高温動作が可能となります。
高温動作は、冷却系の簡素化や、短時間大電流対応など、システム全体のメリットがあります。
それらを実現するには、デバイスの実装技術、とりわけ接合技術が重要で、熱特性、電気特性 に加え、耐熱性が必要です。
パワー半導体の接合技術は、Agナノ系、合金系など、さまざまな技術が研究されていますが、低コストを狙ったCuナノ系も候補の1つと思われます。そこで、 Cuナノ粒子接合を中心として、パワーサイクル信頼性などについて説明します。
パワーデバイスの接合技術の耐熱性評価を中心に説明します。耐熱性評価の方法そのものも、検討されている状況で、これから変わっていく可能性も高いと思います。しかし、「何かがなければ、やれない」といった受身な姿勢では、技術は進化しません。ないのであれば、たとえ専門外であっても、先に自分がやってみようといったチャレンジ精神で、技術開発に臨まれることをお勧めします。
1.. EV/HV技術
2..次世代パワー半導体
3..パワー半導体用接合技術
3.1 接合技術に求められる要件
3.2 接合技術の概況
3.3 Cuナノ粒子接合
3.3.1 熱特性および予測
3.3.2 信頼性評価
【質疑応答・名刺交換】
受講料
64,800円(税込)/人
関連セミナー
もっと見る関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
全樹脂電池とは?その仕組み、全個体電池との違いをわかりやすく解説
【目次】 近年、エネルギー技術の進化が目覚ましく、特に電池技術はその中心的な役割を果たしています。中でも「全樹脂電池」は、軽量で安全... -
IGBTとは?原理と仕組み、その利用法をわかりやすく解説
【目次】 IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)は、現代の電力エレクトロニクスにおいて非常に重要な役割を果たしています。特に、... -
熱雑音とは?知っておくべき基礎知識と対策法をわかりやすく解説
【目次】 電子機器や通信システムにおいて、熱雑音は避けて通れない問題です。特に、精密な測定や高性能なデバイスを求める現代においてその... -
SiC MOSFETとは?仕組みや利用における利点と欠点について解説
【目次】 シリコンカーバイド(SiC)金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)は、次世代のパワーエレクト...