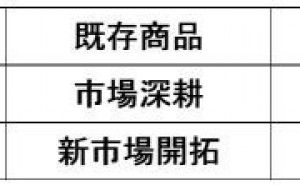DEA(包絡分析法)とは?事業体の効率をどう評価するのか、わかりやすく解説
1. DEA (Data Envelopment Analysis)とは
DEAとは、Data Envelopment Analysis(日本語では包絡分析法)の略語で、多入力多出力システムの相対的な効率を評価する手法として1978年にCharnes、CooperとRhodes3名の連名論文で提案されました。 DEAでは、すべての評価対象に対して、評価対象ごとに効率が最大になるように異なる評価基準を用いるのが特徴であり、簡便で広く適用できる利点があります。 財務会計を使った方法では評価が難しい学校の教育プログラムや、非営利公企業(図書館,公立病院等)の効率性を相対的に評価するなど幅広い分野で利用されています。
2. 金額で評価できない項目も含めて複数の入力と出力の関係を分析
DEAの基本的な考え方は、各ユニットが最大の出力を得るために最小の入力を使用しているかどうかを評価することで、効率的なユニットと非効率的なユニットを識別することができます。複数の入力と出力を持つ複数のユニット(企業、組織など)の効率性を評価するための数理モデルとして、金額で評価できない項目も含めて、各ユニットの効率性を比較することができます。
DEAを使用する際には、まず入力と出力を定義し、各ユニットのデータを収集します。その後、数理モデルを使用して各ユニットの効率性を評価し、効率的なユニットと非効率的なユニットを特定し、金額で評価できない項目も含めて複数の入力と出力の関係を分析します。金額で評価できない項目がある場合でも、DEAを使用することで効率性を客観的に評価することができます。
3. 評価対象ごとに複数の入力項目間の重み付けを効率が最大になるよう調整
DEAは、複数の入力項目と複数の出力項目を持つ複数の評価対象を比較するための効率性分析手法で、各評価対象の入力と出力の効率を評価するために、それぞれの入力項目に対する重み付けが行われます。この重み付けは、各評価対象が他の評価対象よりも優れているかどうかを示す指標となります。
効率が最大になるように重み付けを調整するには、各評価対象が最適なバランスで入力を使い、出力を生成している状態を指します。つまり、DEAでは、各評価対象が他の評価対象よりもより多くの出力を生成するために、より少ない入力を使用しているかどうかを評価することが重要です。重み付けを調整することで、各評価対象の効率性を最大化し、改善の余地がある領域を特定することが可能となります。
4. 個別の実情にあった客観的な評価
DEAを使用して個別の実情に合った客観的な評価を行うには、以下の手順が一般的に推奨されています。
①データの収集: DEAを適用するために必要なデータを収集します。これには、各ユニット(企業、組織、部門など)の入力と出力データが含まれます。
②モデルの設計: DEAモデルを設計し、適切な入力と出力変数を定義します。DEAには、CCRモデルやBCCモデルなどさまざまなモデルがあります。
③モデルの最適化: 設計したDEAモデルを最適化し、各ユニットの効率性を評価します。これにより、各ユニットの相対的なパフォーマンスが明らかになります。
④結果の解釈: DEAの結果を解釈し、効率性の低いユニットや改善の余地があるユニットを特定します。これにより、改善のための具体的な施策を検討することができます。
5. DEAモデルの種類と選択
DEAには、いくつかの主要なモデルが存在します。最も基本的なものがCCRモデルで、これは収穫一定(CRS: Constant Returns to Scale)を前提としています。CRSとは、入力が2倍になれば出力も正確に2倍になる、という単純な規模の仮定です。このモデルは、入力と出力の間に直線的な関係があると仮定し、技術的効率性を全体的に評価します。
一方、BCCモデルは、収穫可変(VRS: Variable Returns to Scale)を前提としています。VRSとは、入力が増えても出力が比例して増えるとは限らないという、より現実的な仮定です。たとえば、ある規模を超えると効率が低下する、あるいは逆に特定の規模で効率が最大化される、といった状況を考慮します。BCCモデルは、純粋な技術的効率性(経営の巧拙)と規模の効率性(事業規模が最適かどうか)を分離して評価できるため、より詳細な分析が可能です。
どのモデルを選択するかは、分析の目的と対象となる事業体の性質によって決まります。たとえば、病院や学校のように、規模の拡大が必ずしも効率の向上に結びつかないと考える場合は、BCCモデルが適しています。逆に、生産性が規模に比例すると考えられる製造業などでは、CCRモデルが有効な場合があります。
6. 効率性フロンティアとベンチマーク分析
DEAの最も重要な概念の一つに、効率性フロンティアがあります。これは、最も効率的な事業体(ユニット)を結んでできる仮想的な境界線のことです。このフロンティア上に位置するユニットは、その入力の組み合わせに対して最大の出力を生み出していると見なされ、効率が100%であると評価されます。
そして、フロンティア上にない非効率なユニットは、フロンティア上のどのユニットをベンチマーク(模範)とすれば効率を改善できるかを示唆されます。このベンチマークは、単一のユニットであることもあれば、複数の効率的なユニットの仮想的な組み合わせであることもあります。DEAの分析結果は、非効率なユニットがベンチマークと比較して、どの入力をどれだけ減らすべきか、あるいはどの出力をどれだけ増やすべきかという具体的な改善目標を提供します。
7. DEAの強みと限界
DEAの最大の強みは、金額で評価しにくい、あるいは評価できない項目(例えば、病院の患者満足度や学校の学習成果)を客観的に評価できる点にあります。また、特定の重み付けを事前に設定する必要がなく、各ユニットにとって最も有利な条件で評価を行うため、公平性が保たれます。これにより、多様な性質を持つ事業体間の相対的な比較が可能になります。
しかし、DEAにも限界はあります。まず、入力や出力の定義が非常に重要であり、不適切な変数を設定すると分析結果が歪む可能性があります。また、DEAは相対的な評価であるため、すべてのユニットが非効率であっても、その中で相対的に最も効率的なユニットがフロンティア上に位置してしまいます。このため、絶対的な効率性を保証するものではありません。さらに、外的な要因(市場環境や規制など)が分析結果に与える影響を直接的に考慮するのが難しいため、分析結果の解釈には注意が必要です。
8. DEAの応用事例と今後の展望
DEAは、公共部門や非営利組織だけでなく、民間企業でも幅広く活用されています。銀行の支店、企業の販売部門、レストランの店舗など、多くの入力と出力を持つ事業体の効率性評価に用いられます。例えば、銀行の支店の場合、入力は従業員数や床面積、出力は預金残高や貸付額といった変数を設定し、効率的な支店を特定することができます。
近年では、DEAを他の分析手法と組み合わせることで、その限界を克服しようとする研究も進んでいます。例えば、DEAで効率性を評価した後に、その結果を回帰分析に組み込むことで、効率性の違いを生む要因をさらに深く探る試みなどです。
DEAは、単なる効率性の数値化に留まらず、組織内のベストプラクティスを特定し、非効率な部分の改善を促すための強力なツールです。今後、ビッグデータやAIの進化と組み合わせることで、より精緻で動的な効率性分析が可能になると期待されています。この手法を理解し、適切に活用することで、組織のパフォーマンスを向上させるための新たな視点を得ることができるでしょう。