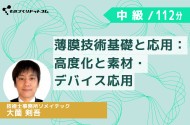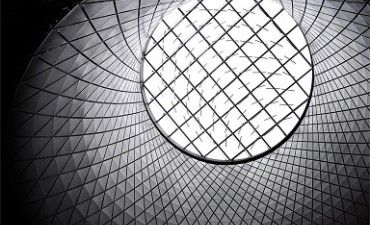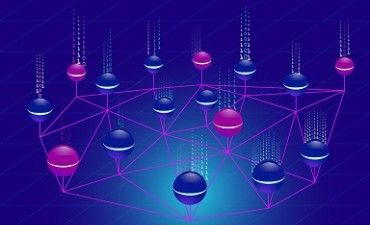類似セミナーへのお申込みはこちら
薄膜を扱う人の基本のキ!
真空成膜における真空技術とスパッタリングのポイントとは?
付着力・応力の制御方法からパーティクルの対策、装置の日常管理・点検のポイント等々、現場で活かせる様々なノウハウを解説します
セミナー趣旨
真空成膜(主にスパッタリングを対象)による機能性薄膜の機能を如何に引き出すかという観点から、教科書に記載されていない・あるいは説明が十分でないため誤解しやすい真空技術とスパッタリングのポイントをお話します。
日常のメンテナンスや業務上のトラブル対策についても述べます。
受講対象・レベル
・スパッタリングなどの真空成膜による薄膜形成に直接あるいは間接的に関わっている人
・蒸着やスパッタなどの真空装置を扱っている人
・薄膜を用いたデバイスや加工品などを扱っている人
・真空技術、薄膜技術に関心のある人
習得できる知識
・薄膜の機能と材料・膜構造などとの関係
・機能性薄膜の作り方のポイント
・真空技術では、真空ポンプや真空計の使い方、高真空の作り方、水の排気、水の排気に関する堀越モデル、ガス配管のパージ方法など
・スパッタリングのカスケードモデル、スパッタ放出角度分布、反射Ar原子、空間原子との衝突、ターゲットの表面変化などが、膜特性と如何に関係するか
・真空・スパッタリングについて科学的・系統的に考えることができるようになります
セミナープログラム
1.薄膜の機能はどこから来るのか
この章ではイントロダクションとして機能性薄膜の機能が何に由来しているのかという問題を考えます。機能性薄膜の由来には3つのタイプがあることを指摘します。具体的な機能性薄膜の例を紹介し、その機能がどのようにして発揮されているのかを見ます。それを元に、さらに、その機能発現のためにポイントとなる事柄から、このセミナで取り上げるテーマについて述べます。
1)機能性薄膜は如何にして作られているか
・薄膜プロセスの具体例
・薄膜の機能の由来
2)本講義では何を明らかにするのか
・薄膜とはどういうものか?
・高真空の作り方 特に水の排気:真空の質が重要。高真空作成のポイントは何か。
・スパッタリング成膜をどう考えたらよいのか:スパッタリングとはどういう現象なのかを理解するのが最も肝心であるという立場から、通常の教科書の説明を超えた部分まで立ち入ろうと考えています。
・スパッタリング装置・プロセスのポイント
・いろいろなスパッタ法は何が工夫されているのか
・日常のメンテナンス、トラブル対策
2.薄膜とはどういうものか?
薄膜とはどういうものかを理解するために、薄膜はどのように形成されるのか?と、薄膜の付着力と応力の2つの面から考えます。薄膜の形成過程には、成長初期段階と膜構造の形成段階とがあります。また、薄膜は基板の上に形成されるので、そこから、付着力と膜応力という特別な問題が生じます。これらは、薄膜の基本の基であり、薄膜を扱う人が常に向きあう問題でもあります。
1)薄膜の形成過程
・核形成・島状成長とそれが見えない場合
・柱状構造とグレインの成長
2)薄膜の付着力と応力
・付着力の本質・強化方法・評価方法
・膜応力とはどういうことか、なぜ生じるのか。制御方法・低減策・評価方法
3.真空の作り方と装置の取扱い・条件設定
真空ポンプや真空計には限界や制限があります。また、高真空をつくるとは、普通は水を排気するということであることを述べます。この「水の排気」の問題を堀越モデルを用いて詳しく検討します(堀越モデルは、水の排気の理解には不可欠なものですが、多くの真空の教科書などでは、殆ど説明されていません) 。ウルトラクリーンテクノロジーに基づくガス配管の排気についても触れます。
1)スパッタリング、蒸着装置の構成と設計要素の意味
2)高真空作成のために必要なことは何か
3)水の排気の理解のカギは「堀越モデル」
・吸着性分子の振る舞い
4)ガス配管の水の排気
4.スパッタリングとはどういうことか?
スパッタリング成膜を
①ターゲットからのスパッタ粒子の放出過程および付随する現象
②スパッタ粒子のターゲットから基板への輸送過程
③基板でのスパッタ粒子の堆積、膜形成過程
の3つの過程に分けて考えます。それぞれの過程で、「スパッタリングは非平衡現象である」をキーワードに、スパッタリングの特徴が何に由来し、何を制御する必要があるか述べます。
①の過程では、スパッタリング現象の本質は、原子衝突の連鎖(カスケード)であり、実用条件のスパッタリングでは、極表面の浅いカスケードであることと、反射が無視できないこと、高速な熱的緩和が起きること、ターゲット表面にミクロなレベルから大きな変化がおきることをのべます。スパッタがプラズマ条件だけでなく、ターゲットとの相互作用で決まることを強調します。
②の過程では、スパッタ粒子は、空間原子と殆ど衝突しない弾道的な輸送から、衝突によって熱化した輸送に、スパッタ圧力によって大きく変化することを述べます。
③の過程では、スパッタ粒子が持つエネルギーの大きさの影響と、Arイオンおよび高速反射Ar原子による照射エネルギーの影響とを区別して理解することが大切であることを述べます。
1)スパッタリング成膜の3つの過程
2)スパッタが非平衡現象であるとはどういうことか?
3)ターゲットからのスパッタ粒子の放出過程および付随する現象
ターゲット表面はアモルファス化するものとしないものがある。
4)スパッタ粒子のターゲットから基板への輸送過程
5)基板でのスパッタ粒子の堆積、膜形成過程
5.スパッタリング装置・プロセスのポイント
1)膜厚均一性
・膜厚を決める要因
・均一化のコツ
・膜質均一性との関係
2)スパッタリング圧力
3)多数回成膜
4)スパッタリングの熱と温度
5)いろいろなスパッタ装置・プロセスの工夫とその意味
パルス電源の利用、デュアルカソード方式
低圧力・高圧力スパッタとイオン化スパッタ
RAS方式など
6.日常のメンテナンス、トラブル対策
1)装置の日常管理・点検のポイント
2)パーティクル発生メカニズムとその対策
・パーティクルの要因とその運動
・「擦れ」・「薄膜剥がれ」・「スプラッシュ」対策
3)薄膜・パーティクルが燃える
4)アーキング(異常放電)への対処、その他の注意点
5)真空装置の省エネ技術
付録 真空・薄膜・スパッタリング・プラズマの参考書、参考資料、学会・研究会などの紹介
<質疑応答>
セミナー講師
元東京理科大学 工学部 第二部 電気工学科 非常勤講師 理学博士 岡田 修 先生
日本電気(株)(現NEC)にて磁性材料開発等の業務担当
日電アネルバ(株)(現キヤノンアネルバ)にて真空成膜プロセス開発・社内技術教育など担当
東京理科大学 非常勤講師 デバイスプロセス、真空工学担当
他に、ものつくり大学 非常勤講師 真空技術、沼津高専 非常勤講師 コンピュータ工学
セミナー受講料
1名41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
受講料
41,800円(税込)/人
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
12:30 ~
受講料
41,800円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、コンビニ払い
開催場所
東京都
【江戸川区】タワーホール船堀
【地下鉄】船堀駅
主催者
キーワード
薄膜、表面、界面技術 生産工学
※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です
開催日時
12:30 ~
受講料
41,800円(税込)/人
※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます
※銀行振込、コンビニ払い
開催場所
東京都
【江戸川区】タワーホール船堀
【地下鉄】船堀駅
主催者
キーワード
薄膜、表面、界面技術 生産工学関連教材
もっと見る関連記事
もっと見る-
ナノテクノロジーとは?基礎から最新応用、未来の課題まで徹底解説
【目次】 1ナノメートルは髪の毛の太さの約10万分の1。ナノテクノロジーとは、原子や分子といった極限の小ささの世界で物質を自在に設計... -
超流動とはどういう現象?仕組みや超伝導との違いなどを詳しく解説
【目次】 超流動とは、物質が極低温において示す特異な現象であり、流体が摩擦なしに流れる状態を指します。超流動の現象(特にヘリウム-4... -
フェルミ準位とは?半導体・金属での違いや応用例をわかりやすく解説
【目次】 フェルミ準位は、物理学や材料科学において非常に重要な概念です。特に半導体や金属の電子構造を理解する上で欠かせない要素となっ... -


![[入門者OK]<br/>この分野の初歩から説明します 初心者向けセミナーです](https://assets.monodukuri.com/img/beginner-mark.png?d=0x0) <教科書にない、実用的な>スパッタリング薄膜の 膜質制御・装置管理とトラブル対策 ~膜質・機能を左右するポイントや現場でのメンテナンス・安全・省エネ対策等~
<教科書にない、実用的な>スパッタリング薄膜の 膜質制御・装置管理とトラブル対策 ~膜質・機能を左右するポイントや現場でのメンテナンス・安全・省エネ対策等~