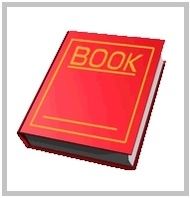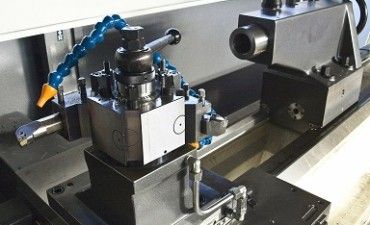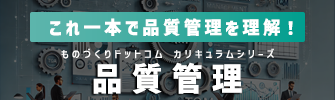疲労破壊解析技術の実務への活用のしかた:実際に実務で活用できる疲労・破壊計算のしかたを多くの計算例題により解説!疲労破壊解析への機械学習の応用事例!
・疲労解析と破壊解析について分かりやすく解説致します!
・理解を促進する計算例題を用意しましたので、大変理解しやすいセミナーになっております。 !この分野のCAEによる計算結果の妥当性の検証に大いに役立ちます!
・この技術をブラックボックス化しないのでよく理解できます。CAE解析結果に振り回されないようになるための実務技術についても分かりやすく解説致します!
・疲労解析ソフトやき裂進展シミュレーションソフトの世界の動向についても解説致します!
※開催日の5営業日前までにお申し込みください
セミナー趣旨
疲労破壊を未然に防止するには、その前過程である塑性変形の理解が大事であり、同時に、時間と共にき裂進展することから、き裂の力学である破壊力学の理解も大事です。一見相反する塑性変形と破壊現象を構築しているそれぞれの技術体系の理解により実務にとって大切な疲労破壊の本質にせまることができます。
構造部材の研究・開発・設計者・技術者において、部材の強度は設計の基本となる重要な因子です。疲労破壊においては、この部材の強度と共に、部材の構造、変動負荷、材料の3大要因を有効に制御し、その防止対策の構築が求められます。本セミナーでは、疲労破壊などの破壊防止に携わる研究・開発・設計者・技術者はその未然防止に有効な指針を取得し、加えてこれから疲労破壊の基礎を学ぶ意欲のある研究・開発・設計者・技術者においては、疲労破壊と破壊力学の基礎知識を得る場となっております。
疲労などの破壊の未然防止が第一である会社の研究・開発・設計者・技術者においては、疲労破壊を狭く詳細に理解することより、疲労破壊を理解し、従事している仕事に生かすことが大事です。
本セミナーでは、疲労破壊の未然防止のため、疲労破壊の主要因である塑性変形、構造物の破壊におけるき裂の力学である破壊力学を疲労破壊と共に平易に説明するとともに、多くの計算練習問題を実際に自分で解いて頂きます。この時に計算のしかた、計算ノウハウなどについても解説いたします。これらの手計算は、有限要素法による疲労解析結果の妥当性の検証に大いに役に立ちます。
受講対象・レベル
- 疲労解析・破壊力学を根底から理解されたいかた
- 疲労解析・破壊力学を習得し実務に役立てたい方
- 疲労解析・破壊力学に関する技術専門書を読んだが理解できなかったという方
- 部下の管理監督上、疲労解析・破壊力学をについての実務上のポイントを理解しておきたいかた
必要な予備知識
- 高校卒業程度の物理、数学の基礎知識。
- 材料力学・金属材料・焼き入れなどの熱処理の基礎知識があれば理解がさらに深まりますが、入門知識からから分かりやすく解説しますので特に必要ありません。
習得できる知識
- 疲労解析・破壊力学をなどの技術を根底から理解できるようになります
- 疲労解析・破壊力学などによる技術を正しく使いこなすことができるようになります
- 疲労解析・破壊力学をいろいろな実務に即して臨機応変に使いこなせるようになります
- 疲労解析・破壊力学についての実務上のポイントを短時間で要領よく理解することができます
- 疲労解析・破壊力学などの技術を駆使して自分で手計算ができるようになります
セミナープログラム
- 金属疲労の基礎
- まず、材料力学と材料強度学の違いは?
- 材料力学とは?
- 材料強度学とは?
- 硬い材料の破壊と柔らかい材料の破壊
- 疲労とは?
- 疲労のメカニズムとは?
- 疲労を発生させる応力とは?
- 繰返し応力とは?
- 変動応力とは?
- 疲労破壊とは?
- S-N線図とは?
- 低サイクル疲労とは?
- 高サイクル疲労とは?
- 超高サイクル疲労とは?
- 高温クリープとは?
- フレッティングとは?
- まず、材料力学と材料強度学の違いは?
- 疲労および疲労解析とは?
- 疲労き裂の発生と進展
- なぜ最初に45°方向に亀裂が入るのか?
- ビーチマークとストライエーション
- 実際にはいろいろな応力が働く
- 破壊事故例の原因別分類
- S-N線図のイメージ図と描き方
- 累積損傷則
- マイナー則
- 修正マイナー則
- 低サイクル疲労・高サイクル疲労
- 低サイクル疲労のヒステリシスループ
- 繰返し応力-ひずみ曲線
- ひずみ基準の疲労寿命予測
- 高サイクル疲労(バスキンの式)
- 低サイクル疲労(マンソン・コフィンの式)
- 統合された疲労寿命式(モローの式)
- ε-N 曲線
- 疲労寿命推定法
- 破壊力学とその使用法
- なぜ破壊力学が必要なのか?
- き裂とは?
- ミクロき裂の発生を抑えるには?
- き裂の変形のしかたとは?
- 応力拡大係数の定義式
- エネルギー解放率とは? その定義式とは?
- J積分とは ?
- J積分の考え方
- J積分の定義式
- パリス則とは?
- 応力拡大係数範囲とき裂進展速度の関係
- パリス則を式で表すと
- 破壊力学パラメータを用いた寿命予測
- 準備
- 絶対的な寿命予測
- 疲労限度と引張強さ・硬さとの関係
- 鉄鋼材料の回転曲げの疲労強度を使用する場合
- 回転曲げ以外の鉄鋼材料の疲労強度と静的強度の比
- 非鉄金属材料(アルミニウム合金、銅合金)の回転曲げ疲労の場合
- 実務のための計算のしかた・ノウハウの説明と計算練習(実際に計算して頂きます)
-手計算による有限要素法による疲労・破壊の解析結果の検証法としてー- 引張強さと硬度から疲労限度を求めてみよう!
- 真中にき裂がある場合の応力拡大係数 KⅠ を計算で求めてみよう!
- 片側にき裂がある場合の応力拡大係数KⅠを計算で求めよう!
- マンソン-コフィンの式から疲労寿命を計算してみよう!
- 破断するまでの寿命を計算で求めてみよう!
- マイナー則および修正マイナー則による累積損傷値の計算
- 修正マイナー則により疲労寿命を推定計算してみよう!
- 疲労解析ソフトの世界の動向
- き裂進展シミュレーションソフトの世界の動向
- 疲労を検知するセンサとは?
- 疲労破壊解析技術への機械学習の応用事例
- 質疑応答
セミナー講師
(社)日本騒音制御工学会認定技士 (社)日本音響学会技術開発賞受賞
有限会社アイトップ 技術コンサルタント 通訳・翻訳
名古屋大学大学院 非常勤講師(英語で応用数学の講義を担当)
工学博士 小林 英男 氏
東京電機大学工学部機械工学科卒業後、東京農工大学大学院工学研究科にて特別研究員 (1990~1994)
大学生時代にESSに所属し、カリフォルニア大学バークレイ校に語学研修、および毎日新聞社後援英語弁論大会で3位入賞。企業からの派遣で東京農工大学大学院工学研究科にて5年間特別研究員(産学協同研究、文部省認定)。東京電機大学第53代ESS部長。英語の勉強にも集中したのは卒業後に世界で活躍できるエンジニアになるため。
大学卒業後、リオン㈱に入社し、騒音・振動の測定・分析・対策、および海外事業部でセールスエンジニアとして従事。 ㈱アマダに勤務し、工場で組立・製造・検査、海外事業部で技術サービスおよび技術コンサルタント、システム事業部で板金加工自動化ライン(FMS)の開発・設計、技術研究所でアマダ製品の低騒音・低振動化および快適音化などの研究開発に携わり大ヒット商品を世に送り出した。上記のように、製造、サービス、設計、開発、研究(製造~研究まで)の一連の実務経験を積んだ。
その後、技術コンサルタントとして独立して25年が経過した。1部上場企業の研究、開発、設計部署を中心に、多くの企業に対し技術指導およびコンサルティングを実施。この間に先進国を中心に25ヶ国以上に出張し、エンジニアとして英語で仕事をするだけでなく、通訳・翻訳なども行う。
セミナーの講師歴は25年間。日刊工業新聞社など主催の多くの技術セミナー・英語セミナー・工業数学セミナー・応用物理数学セミナーの講師を行ってきている。この間に専門学校や大学で非常勤講師も行ってきた。
特に、日刊工業新聞社主催のセミナー講師歴は長く10年以上。機械学習・深層学習・AIを加速化させる技術指導にも力を入れてきた。
また、幾多の難局を乗り越えて技術指導を成功させてきた。本セミナーでは、その時々の実際の実務経験もまじえながら分かりやすく解説致します。
セミナー受講料
¥44,000/人(テキスト代、消費税含む)
1社から複数名様が同時にお申込みされた場合に限り、2名様目から1名様ごとにお1人様当たり¥5,000割引きさせて頂きます。つまり2名様目からお1人様当たりの受講料が¥39,000(テキスト代、消費税含む)になります。セミナー受講料のご請求書は、代表お申込者(お一人目の受講者様)に郵送いたします。
<テキストについて>
テキストは、原則としてセミナー開催日の3営業日までに受講者様に届くように郵送致します。場合によっては、当社の独自の判断によりテキストをPDFファイル化しメールに添付してお送りすることもあります。
受講について
Zoomを使用したWebinarになります。このZoomセミナー開催日の前日の午前中までに、Zoomセミナーへご参加頂くためのURLとセミナーIDをメールにてご連絡させて頂きます。セミナー当日は、5分前までにはご入場下さい。
ご参加時にお名前がわかるようにして頂く様お願い申し上げます。これは、入場できずにいる方などを見つけるためのものですのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
社内からZoomセミナーに参加できない場合は、テレワークの一環としてご自宅などからご自分のパソコンなどでご受講頂くこともできます。
受講開始時にはマイクはオフに設定下さい。ビデオもオフに設定して頂くことができます。この場合は受講者様の映像は、セミナー主催者およびセミナー講師には届きません。また、ビデオ設定をオンにしても背景画像をご選定頂ければ受講者様の背後映像はセミナー主催者およびセミナー講師には届きません。
セミナー受講中にご質問がある場合は、チャット欄にご記入頂く様お願い申し上げます。ご質問へのご解答は原則としてセミナー受講時間中に完了するように致します。
目安ですが、講習時間約60分に対し約10分間を休憩時間と致します。
昼食時間は、11:45~12:45です。
また、セミナーテキスト内に記載されていることへのご質問は、セミナー受講後(例えば1ヶ月後とか半年後)でも無料で本セミナーの講師がZoomソフトやメール・電話を使用してご解答致します。
【お申込の前のお願い】
ご使用のPC・通信回線にセキュリティなどの制限がある場合、Zoomを利用できない場合があります。事前に下記のサイトにて、Zoomの接続・利用についてご確認ください。
・テスト画面: 『Zoomをテストする』
受講料
44,000円/人